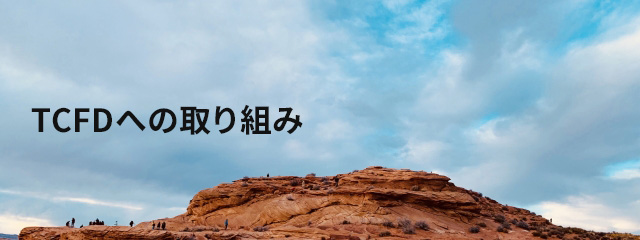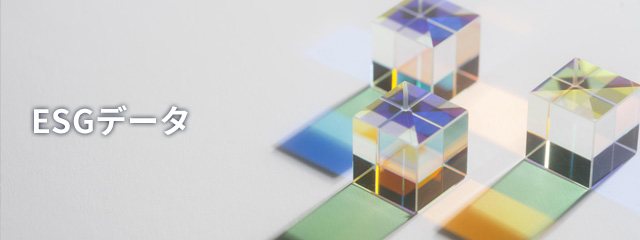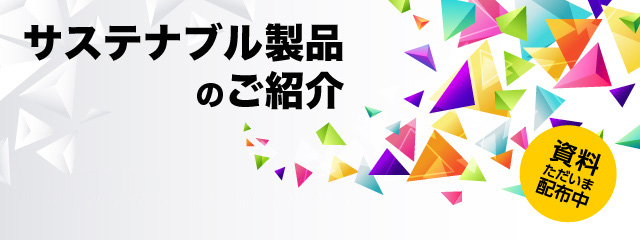サステナビリティ
ニュース
- 2025年12月4日
- 研究開発
- 「DICテクニカルレビュー」を再開しました。サイエンティストメンバーを中心に執筆した6本のレビュー記事を新たにご紹介します。
- 2025年12月4日
- 研究開発
- 「受賞歴・外部発表実績」を更新しました。DICの研究開発活動における受賞歴と、技術メンバーによる外部発表実績をご紹介しています。
- 2025年12月4日
- サステナビリティ
- DIC、物流におけるCO₂排出量の可視化を開始
- 2025年11月27日
- サステナビリティ
- DICグループ、製品カーボンフットプリントの算定方法で国際規格準拠の第三者認証を取得
- 2025年11月13日
- サステナビリティ
- [Vision Watch]未来を創る仲間と出会う場所 ― アジア各地域から集うDICの技術者育成ストーリー